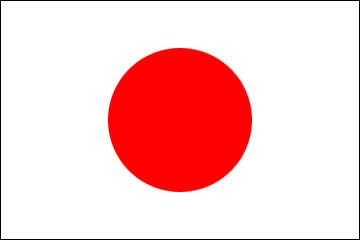アフリカにおける黄熱の流行(黄熱ワクチンを接種し、渡航時には忘れず接種証明書を携行してください。)
平成28年5月20日
対象国:アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ
1 黄熱の発生状況
(1) アンゴラでは、2015年12月以降、首都ルアンダを中心に感染者数が急速に増加しており、2016年5月11日現在、2,267の疑い例(うち、感染確定696例、死亡293例)が報告されています(世界保健機関(WHO)発表)。
(2) 隣国であるコンゴ民主共和国では、3月22日にアンゴラからの輸入例が確認され、同国政府は、4月23日、黄熱アウトブレイクを発表しました。5月11日現在、44の疑い例(感染が確定した41例のうち、39例がアンゴラからの輸入例)が報告されています。
(3) コンゴ民主共和国のほか、東アフリカのケニア及び中国においても、アンゴラからの輸入症例が、それぞれ、2例及び11例報告されています。
(4) ウガンダでは、2016年3月、首都カンパラ市の南西約130キロにあるマサカ地域で黄熱の感染者が確認され、5月11日現在、7地域で51の疑い例(うち、感染確定7例)が報告されています。なお、ウガンダでの黄熱の流行は、アンゴラでの流行とは関連性がないとされています。
(5) アンゴラ及びコンゴ民主共和国政府は生後9か月以上のすべての渡航者に対して、またウガンダ政府は生後6か月以上のすべての渡航者に対して、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求めています。流行状況の変化に伴い、これらの国やその周辺の国々では黄熱予防接種証明書に対する対応が変わる可能性があります。そうした国々に渡航・滞在を予定している方及び既に滞在中の方は、渡航先の在外公館等から最新の関連情報を入手するとともに、以下3(4)を参考に、黄熱ワクチンを必ず接種し、渡航時には黄熱接種証明書を忘れず携行するようにしてください。
2 世界保健機関(WHO)の対応
WHOは、アフリカでの黄熱の流行に関し、5月19日、国際保健規則(IHR)緊急委員会の第1回会合を開催しました。同委員会の見解を踏まえ、WHO事務局長は、現在の流行状況は深刻かつ重大な懸念事項であり、集中的な対策が求められるが、現時点において、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC、 Public Health Emergency of International Concern)」には該当しない、としています。
3 黄熱について
(1) 感染経路
黄熱は、黄熱ウイルスに感染した蚊(ネッタイシマカ)に刺されることでかかる全身性の感染症です。アフリカ(主に中央部)と南アメリカ(主にアマゾン地域)等で感染者が報告されています。ヒトからヒトへ感染することはありません。
(2) 症状
通常3~6日の潜伏期間の後、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐などの症状を示します。一部が重篤化し、黄疸などを呈し、致死率は20~50%に達します。
(3) 治療方法
特別な治療法はなく、対処療法が行われます。
(4) 予防
黄熱は、黄熱ワクチンの接種により予防することができます。1回の予防接種で終生免疫を獲得することができます。黄熱リスク国・地域に渡航する際には、黄熱ワクチンの接種が推奨されるほか、国によっては入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が求められることがあります。
黄熱予防接種証明書は、接種後10日後から有効となりますので、渡航を計画されている方は、早めに接種を行うことが大切です。なお、黄熱予防接種は、日本国内では指定された全国24か所の施設以外では接種することができません。接種は予約制で、渡航ピーク時には予約が取れないこともありますので、接種が必要な場合には、早めに予約するようにしてください。また、アレルギーや病気療養中、妊娠中の方などは接種ができない場合もありますので、詳しくは最寄りの接種機関にご相談ください。
(参考)平成28年7月11日以降、黄熱予防接種証明書の有効期間が10年から生涯有効へ延長されます。5月19日の国際保健規則緊急委員会では、有効期間延長の措置を早期に実施することを求めていることから、前倒しで実施される場合があります。また、黄熱ワクチンは生ワクチンのため、後日、別のワクチンを接種する際には27日以上の間隔を置く必要があります。渡航先によっては黄熱以外にも接種が勧められる渡航者用ワクチンなどもありますので、早めに黄熱接種機関に相談するようにしましょう。
黄熱については、以下の厚生労働省検疫所のホームページにて詳細情報を提供しておりますので、あわせてご参照ください。
http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
4 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(現地大使館連絡先)
○在アンゴラ日本国大使館
電話 :222-442007/441662
国外からは:(国番号244)222-442007/441662
ホームページ:https://www.angola.emb-japan.go.jp/
○在コンゴ民主共和国日本国大使館
電話:081-555-4731~4
国外からは(国番号243)81-555-4731~4
ホームページ:https://www.rdc.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ウガンダ日本国大使館
電話:(市外局番041)4349542~4、
国外からは(国番号256)41-4349542~4
ホームページ:https://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm
1 黄熱の発生状況
(1) アンゴラでは、2015年12月以降、首都ルアンダを中心に感染者数が急速に増加しており、2016年5月11日現在、2,267の疑い例(うち、感染確定696例、死亡293例)が報告されています(世界保健機関(WHO)発表)。
(2) 隣国であるコンゴ民主共和国では、3月22日にアンゴラからの輸入例が確認され、同国政府は、4月23日、黄熱アウトブレイクを発表しました。5月11日現在、44の疑い例(感染が確定した41例のうち、39例がアンゴラからの輸入例)が報告されています。
(3) コンゴ民主共和国のほか、東アフリカのケニア及び中国においても、アンゴラからの輸入症例が、それぞれ、2例及び11例報告されています。
(4) ウガンダでは、2016年3月、首都カンパラ市の南西約130キロにあるマサカ地域で黄熱の感染者が確認され、5月11日現在、7地域で51の疑い例(うち、感染確定7例)が報告されています。なお、ウガンダでの黄熱の流行は、アンゴラでの流行とは関連性がないとされています。
(5) アンゴラ及びコンゴ民主共和国政府は生後9か月以上のすべての渡航者に対して、またウガンダ政府は生後6か月以上のすべての渡航者に対して、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求めています。流行状況の変化に伴い、これらの国やその周辺の国々では黄熱予防接種証明書に対する対応が変わる可能性があります。そうした国々に渡航・滞在を予定している方及び既に滞在中の方は、渡航先の在外公館等から最新の関連情報を入手するとともに、以下3(4)を参考に、黄熱ワクチンを必ず接種し、渡航時には黄熱接種証明書を忘れず携行するようにしてください。
2 世界保健機関(WHO)の対応
WHOは、アフリカでの黄熱の流行に関し、5月19日、国際保健規則(IHR)緊急委員会の第1回会合を開催しました。同委員会の見解を踏まえ、WHO事務局長は、現在の流行状況は深刻かつ重大な懸念事項であり、集中的な対策が求められるが、現時点において、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC、 Public Health Emergency of International Concern)」には該当しない、としています。
3 黄熱について
(1) 感染経路
黄熱は、黄熱ウイルスに感染した蚊(ネッタイシマカ)に刺されることでかかる全身性の感染症です。アフリカ(主に中央部)と南アメリカ(主にアマゾン地域)等で感染者が報告されています。ヒトからヒトへ感染することはありません。
(2) 症状
通常3~6日の潜伏期間の後、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐などの症状を示します。一部が重篤化し、黄疸などを呈し、致死率は20~50%に達します。
(3) 治療方法
特別な治療法はなく、対処療法が行われます。
(4) 予防
黄熱は、黄熱ワクチンの接種により予防することができます。1回の予防接種で終生免疫を獲得することができます。黄熱リスク国・地域に渡航する際には、黄熱ワクチンの接種が推奨されるほか、国によっては入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が求められることがあります。
黄熱予防接種証明書は、接種後10日後から有効となりますので、渡航を計画されている方は、早めに接種を行うことが大切です。なお、黄熱予防接種は、日本国内では指定された全国24か所の施設以外では接種することができません。接種は予約制で、渡航ピーク時には予約が取れないこともありますので、接種が必要な場合には、早めに予約するようにしてください。また、アレルギーや病気療養中、妊娠中の方などは接種ができない場合もありますので、詳しくは最寄りの接種機関にご相談ください。
(参考)平成28年7月11日以降、黄熱予防接種証明書の有効期間が10年から生涯有効へ延長されます。5月19日の国際保健規則緊急委員会では、有効期間延長の措置を早期に実施することを求めていることから、前倒しで実施される場合があります。また、黄熱ワクチンは生ワクチンのため、後日、別のワクチンを接種する際には27日以上の間隔を置く必要があります。渡航先によっては黄熱以外にも接種が勧められる渡航者用ワクチンなどもありますので、早めに黄熱接種機関に相談するようにしましょう。
黄熱については、以下の厚生労働省検疫所のホームページにて詳細情報を提供しておりますので、あわせてご参照ください。
http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
4 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(現地大使館連絡先)
○在アンゴラ日本国大使館
電話 :222-442007/441662
国外からは:(国番号244)222-442007/441662
ホームページ:https://www.angola.emb-japan.go.jp/
○在コンゴ民主共和国日本国大使館
電話:081-555-4731~4
国外からは(国番号243)81-555-4731~4
ホームページ:https://www.rdc.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ウガンダ日本国大使館
電話:(市外局番041)4349542~4、
国外からは(国番号256)41-4349542~4
ホームページ:https://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm